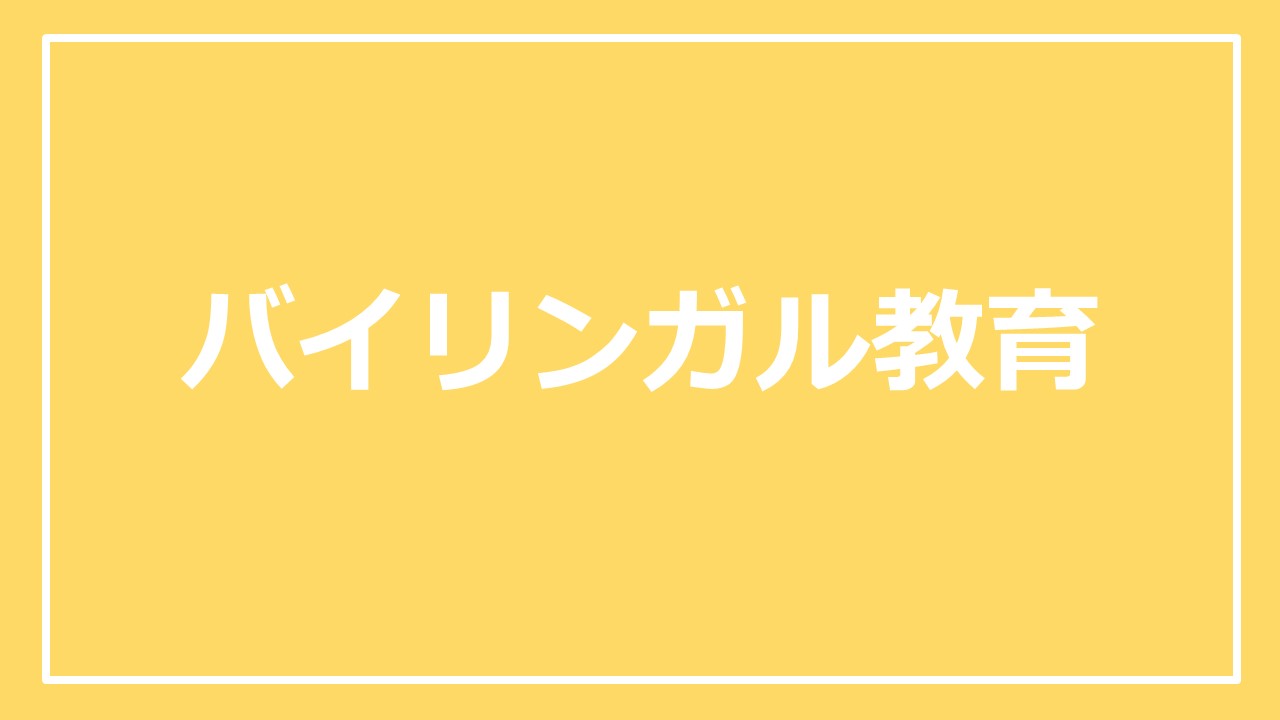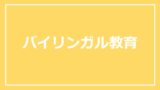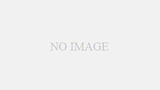こんにちは、いずみです!
前回の記事では、1年半もかけてなぜ日本語学習でたいした成果が出なかったのか、その経緯と原因について書きました。
今回は、どうやって不安定な学習から継続的な学習にこぎつけたかについて書きます。
ご褒美の導入
子供はもうすぐ7歳。時間はどんどん過ぎていくのに、ちゃんと成果を感じられる学習方法すら見つかってない…。
1年半が過ぎても息子がひらがな・カタカナもマスターできておらず、学習の習慣化もできてないことに焦った私は、ご褒美を導入することを決めました。
ご褒美を使うことにした理由
実は、私はご褒美にネガティブなイメージを持っていました。ご褒美について調べたわけでもないのに、ご褒美で釣って勉強させるなんてとんでもない、そんなことをしたらくせになるしきりがないと思っていたんです。
さらに、学習初期のまだ余裕がある段階では「遊び感覚で、楽しみながら日本語の読み書きを身につけることができたらいいな♪ そういうのだったら子供も嫌がらずに取り組んでくれるはず!」などと夢見てもいたので、夜なべして手作りした50音かるたで子供と遊んでみたりなど、まずは思いつく方法は試してみました。
一方で、日本の小学生は「遊び感覚の学習を短時間やって日本語の読み書きを身につける」のではなく、学校の国語の授業+宿題もがっつりやって身につけるわけです。小学校時代、宿題として書き取りや日記が毎日のように出ていたと記憶しています。
なので、自分の経験を振り返ると、
「遊び感覚の学習でちゃんと読み書きが身につくんだろうか?(身につくわけがない)」
「継続的にある程度の学習時間を投入して量もこなさないと、日本語は身につかないのでは?」
とうすうす思っていました。
結局、しばらく試してみたけれど、「遊び感覚でありながら、しっかり効果も感じられる学習方法」には出会えず…。1年半たっても学習を習慣にすることもできていませんでした。子供はもうすぐ7歳という頃で、現地の小学校にも入学し、焦りは募るばかりでした。
親子関係が悪くなるくらいならバイリンガル教育はあきらめようと思っていたし、実際何度もあきらめそうになりました。でも、日本語を保持してほしいという思いを捨てきれませんでした。一番の理由は、息子が日本語ができないと私側の親戚と意思の疎通ができなくなるからです。
そこで、ご褒美を使うことに抵抗がありつつも、万策尽きてご褒美に手を出した…という感じです。
ご褒美で釣って大丈夫?
以前の私も含め、ご褒美を使うことにためらいや抵抗があるという人は、
・ご褒美をあげると、勉強する目的がご褒美をもらうことになるのでは?
・ご褒美がないと勉強しない子になってしまうのでは?
などがその理由だと思います。
ご褒美を導入するにあたって、いろいろ調べました。
ご褒美を使うことのメリット
とりあえずやってみて、ご褒美の悪影響がひどいと感じたらご褒美を使うのは中止しようと決め、ご褒美付きでの学習を始めました。
結果は、息子が嫌がらずに学習に取り組んでくれるので、親子共にストレスがなくなりました。さらに、ご褒美に釣られてやっているうちに、学習することが習慣化しました。
再スタート後に気をつけたこと
ご褒美を取り入れたことで日本語学習がうまくいくようにはなりましたが、学習に取り組む上で気をつけたこともあります。下の記事にまとめました。
息子は学習を習慣化できたことで、忘れる部分が少なくなり、やり直しに費やす時間が少なくなりました。
すると、学習が前進するスピードが速くなり、「自分で書ける」「自分で読める」という実感が持てたせいか、学習時間外でも自発的に何かを読んでみたり書いたりするようになりました。まだ本格的な読書ではありませんが、以前と比べるとすごい成長です。
最後に
ご褒美を導入し、学習の取り組み方にも気をつけて、「子供任せの不安定な学習」から「親子ともにストレスなく継続できる日本語学習」という形に無事移行できました。
うちの子が現在の方法で日本語学習に取り組み始めたのは、ほぼ7歳の時でした。
2024年2月現在、継続は18か月目に入っています。5歳半からの1年半の学習の貯金があったのでゼロからのスタートではないですが、今の方法で始めてからの伸びの方がはるかに大きいし速いです。
1年半もあーでもないこーでもないと試行錯誤し、いろいろ試しても思ったような成果が出ずに絶望し、何度もバイリンガル教育をあきらめかけていたのがうそのようです(現実でしたが…)。
まだ時間に余裕があるのであれば、スモールステップで学習を習慣化するのがいいと思います。
でも、当時のわが家のように「もう待ったなし!」「切羽詰まっている」という状況であれば、日本語学習にご褒美を使うのも1つの手だと思います。
それでは、また!