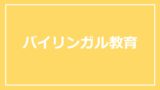こんにちは、いずみです!
子供に家庭学習を習慣にしてほしいのに、うまくいかないとストレスですよね。口うるさく言いたくないのに、つい子供とバトルになってしまったり…。
私は長いあいだ試行錯誤し、だいぶ遠回りしてしまいましたが、2024年2月現在、小学生の息子は日本語学習を約1年半継続できています。
今回は、家庭学習が円滑に進むように、わが家で行ってきた工夫を紹介します。
目次
■まず学習を習慣化する
■学習をスムーズに行うための工夫
・学習のハードルを低くする
・学習記録をつけて子供の頑張りを可視化
・少しでも楽しく勉強に取り組める工夫をする
・学習の取り組み方に柔軟性を持たせる
・家庭学習のルールの適用に融通を利かせる
・変更がある時は予告する
■最後に
まず学習を習慣化する
学習を習慣化するために、息子が自分から勉強することを選ぶような仕組み作りをしました。
「学習するのが当たり前」「学習は生活の一部」という状態になれば、「やる・やらない」に関して親子間のバトルがなくなるので、家庭学習がとてもラクになります。
※長い試行錯誤の末、どうやって学習の習慣化にこぎつけたかはこちら。
学習をスムーズに行うための工夫
学習をスムーズに行うために、以下のような工夫もしました。
学習のハードルを低くする
子供さんが学習をやりたがらない場合、最初は「これは少なすぎでは?」と思うくらい余裕でこなせる学習量にするのがおすすめです。まずは「学習を習慣にすること・継続すること」を重視し、学習が子供の生活の一部になる状態を目指します。
家庭学習が習慣化していない段階で、子供にとって負担な学習量や内容にしてしまうと、勉強が嫌になったり家庭学習をやめてしまうリスクがあります。
たとえば、勉強時間が1日1分と聞くと「少なすぎ」と思う方がほとんどだと思います。でも、最初1分で始めたからといって、ずーっと1分しか学習しないわけではありません。やっているうちに学習することに慣れるし、少しずつ読み書きができるようになって、子供自身が成長を実感できるようにもなります。「余力がある」と感じたら無理のない範囲で徐々に増やしていけばいいです。
学習量が負担になって学習そのものをやめることになるくらいなら、続けるためにまずは1日3分でも2分でも、なんなら1分でもいいので、いったん子供が負担に感じない量にまで減らすのが遠回りなようで近道だと思います。
学習記録をつけて子供の頑張りを可視化
手の込んだものでなくていいので、学習記録をつけることは非常におすすめです。子供の頑張りを可視化してあげれば、「自分はこれだけできたんだ」という自信がつき、それも学習継続のモチベーションとなる可能性があるからです。
うちでは、無料ダウンロードできるカレンダーを印刷し、学習をしたらシールを貼っています。やらなければ空白ができるので一目瞭然。そして息子自身が自分の頑張りを認識するように、「大人でも何かを始めて、それを続けるのは難しいんだよ。〇日以上も続いてすごいね」と折に触れ話すようにしました。
以前は、勉強をやろうが10日休もうがこれっぽっちも気にしていなかった息子ですが、休まずに勉強を続けた期間が10日、30日、50日…と長くなるにつれ、この記録を途切れさせたくないという気持ちが徐々にわいてきたようで、そのことも学習を継続するモチベーションとなっています。
少しでも楽しく勉強に取り組める工夫をする
勉強は習慣化するまではしんどいもの。なので、お子さんが少しでも勉強に楽しく取り組めるといいですよね。
うちの場合は、小さなことですが、家庭学習には息子が大好きなフリクションボールペンを使っていいことにしています。色も、なに色を使ってもOK。
小学生は勉強に鉛筆を使うのだろうと思いますが、鉛筆を使うことを強制する理由を思いつかなかったし、文房具好きの息子が、お気に入りの文房具を使うことで、少しでも楽しく勉強してくれればいいと思っています。
学習の取り組み方に柔軟性を持たせる
「学習メニューをがっちり固定し、どんな場合でもそれをやらせる」というふうにせず、子供が疲れている時や急な予定が入った時などは、量を減らしたり負担が少ない選択肢を選べるようにするといいと思います。ルールを守らせることが目的ではなく、まずは日本語学習を習慣化することが重要だからです。
学習の取り組み方に柔軟性を持たせると、子供も継続しやすいと思います。
家庭学習のルールの適用に融通を利かせる
上の内容と少しかぶりますが、ルールの適用に融通を利かせる(=できなくても大目に見る、見逃す)ことも結構重要だと思います。
学習が定着して数か月たった頃、理由は忘れましたが、息子が一度だけうっかり日本語学習を忘れてしまったことがありました。私はそのことに気づいていましたが、あえて何も言いませんでした。学習することを覚えておくのも息子の役目で、私は何も言わないというルール(※)にしていたからです。
(※最初のうちは、息子が学習を忘れていると思ったら声掛けをしていましたが、学習が定着するにつれ、ルールも少しずつレベルアップさせていきました)
翌日、息子は突然ハッとして、「昨日、にほんご忘れた…」と言いました。ものすごく心が痛みましたが、「そうだね。残念だけど…」と言うと、息子はショックのあまり泣きだしました。90日、100日…と一日も休まず学習を続けてきたということが、いつの間にか彼の中で自慢できることになっていたようです。
そこでこの時は、「勉強するのを忘れたのはこの数か月で昨日が初めてだから、今回だけは特別に、昨日の分を今日やったらOKということにしてあげる。でも、これからは特別はないからね」と言うと、「わかった!」と大喜びで2日分の勉強をやり始めました。
約束ごとの設定と、それをどのくらい厳密に守らせるかというのは難しくて、わが家でも試行錯誤しました。厳しすぎると子供がやる気をなくす恐れがあるし、大目に見てばかりだとなかなか習慣化につながらないと感じます。
この時は、ルールを定着させるのも重要だと思ったので、実は「かわいそうだけど大目にみない」という方向に行きかけていました。…が、すごくショックを受けている息子を見ると、「100日以上も続けてきたのに、連続記録が途切れた。もういいや…」と自暴自棄になり、勉強自体やめてしまうんじゃないかと思いました。大体、それ以前と比べるとものすごく頑張ってきたのです。なので、とっさに「今回だけは特別に…」としたのですが、あの時ルールを定着させることを優先しなくてよかったです。
学習を習慣化するには、休まず毎日やることはやはり重要だと思うので、それとの兼ね合いが難しいのですが、子供がやる気を失わないためには、子供が約束を守れなくても、大目に見ることが必要なこともあると学んだ出来事でした。学習習慣が完全に定着するまでは、「本当に勉強をするつもりだったのに、うっかり忘れてしまった」ということはあると思うので。
私自身不安に感じたのが、1回でもこんなふうに大目に見てしまうと、子供は「約束事を守らなくてもママは見逃してくれるんだ…」と学習してしまうのでは?ということ。でも、結果的には大丈夫でした。
それに、すでに書いたように、休まずに勉強を続けた期間が長くなるにつれ、続けることに対してよい意味での執着が生まれるので、簡単にサボろうという気持ちにはなりにくいと思います。
実際、息子は学習をやり忘れないことや時間に一層気をつけるようになったし、この時のようなことはそれ以来一度も起こらずに1年以上がたちます。
変更がある時は予告する
誰だっていきなり「今から〇〇をやれ」と言われたら嫌ですよね。
「今日から〇〇しよう」となると、うちの子もたいてい反発します。〇〇とは彼にとって何かしら負荷のかかることだったり、ルールの変更だったり(「毎日やってる漢字ドリルを1ページ増やす」とか)。でも、「来週から、週末は日本語学習を午前中に終わらせることにしてほしい」のように事前に告知しておくと、心の準備ができるようで、(最初のうちは文句言ったりしつつも)たいてい受け入れてくれるので、ギスギスしないで済みます。
最後に
以上、家庭学習をスムーズに行うためにわが家で行ってきた工夫でした。
息子が5歳半の頃に日本語教育をスタートしてから7歳までの1年半は試行錯誤の連続でしたが、こうすれば息子は学習に取り組みやすいのでは?と思ったことを試してきました。
海外で現地校に通う子にとっての日本語学習のように、子供自身がモチベーションを見出しにくい学習では、なるべく子供が負担を感じないようにすることも重要だと思います。
少し工夫をすることで家庭学習を行いやすくなると思うので、合いそうなものがあれば試してみてくださいね。
それでは、また!