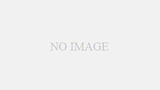こんにちは、いずみです!
息子が小2の時に、『新レインボー小学国語辞典 改訂第7版』という辞典を購入しました。
でも、この辞典は結局使わなくなってしまいました。時間をかけ、よく検討した上で選んだつもりだったのですが…。
この国語辞典を使う中で、どういう点が小2だった息子には使いにくかったのかわかりました。
そこで今回は、低学年用の国語辞典選びに失敗した私が、国語辞典を選ぶ際に重要だと思うことについて書きたいと思います。
国語辞典選ぶ際の参考になったら嬉しいです。
去年、国語辞典を選ぶ際に気にしたポイント
国語辞典を選ぶにあたって注意したことを一応書いておきます。
●サイズ
●収録語数
●写真・イラストの数
●発売日
サイズ
サイズは、多くの国語辞典でB6判とワイド版(A5判)から選べるようになっています。
学校で使うために買うのであれば、コンパクトで軽めのB6サイズを選ぶ方が多いのでしょうが、うちの場合は家でしか使わないのでコンパクトさや重さは重視しておらず、「見やすさ」という点でワイド版希望。
収録語数
もし説明のわかりやすさに大差がないとすれば、収録語数が多いにこしたことはないと思いました。
写真・イラストの数
小学生用なので、写真やイラストが多いと辞書を引くのが楽しく感じられるのではないでしょうか。わかりやすさの点でも、写真やイラストが多いのはよいと思います。
発売日
よほどの理由がない限り、発売から年数が経っているものは避けたいと思いました。
改訂されたものは新たな工夫もされているでしょうし。
ちなみに、最終候補となったのは以下の3点。
3点ともすべての漢字にふりがな付き、フルカラーという点は同じで、漢字ポスターなどの付録や特典もいくつか付いています。
| チャレンジ小学国語辞典 第2版(ベネッセ) | 新レインボー小学国語辞典 改訂第7版(学研) | 例解学習国語辞典 第十二版(小学館) | |
| サイズ | B6判 | B6判とワイド版(A5判) | B6判とワイド版(A5判) |
| 収録語数 | 35,600語 | 43,000語くらい? | 40,900語 |
| 写真・イラストの数 | 1,700点 | 1,400点 | 1,100点 |
| 発売日 | 2020/12/15 | 2023/12/7 | 2023/11/29 |
| その他 | ●気持ちを表す表現を学べるコラム、言葉の使い分けが身に着くコラムなど(60点以上) ●漢字ポスター | ●自分の気持ちにふさわしい言葉を選べるようになるためのコラム(300点以上) ●漢字ポスターなど | ●「名探偵コナンの10才までに覚えたい難しいことば1000特別版」 ●漢字ポスター |
低学年用の国語辞典選びで一番重視すべきポイントは?
というわけで、去年、国語辞典を購入するにあたっては、時間をかけていくつもの国語辞典の説明を読み込み、上記のポイントをチェックし、よく検討した上で『新レインボー』を選びました。
なのに、失敗しました。
実際に使ってみて思ったのは、「説明の分かりやすさ」に比べると他の点はさほど重要ではない、ということ。辞典選びで一番重視すべきはやはり、
「辞典を使う子供が理解できる説明になっているかどうか」
だと思います。
実際、『新レインボー小学国語辞典』は非常に高評価の辞典ですが、息子にとっては言葉の説明が難しかったため、使い続けることはできませんでした。
そこで、私が考える、低学年のお子さんに国語辞典を買うにあたっておすすめしたいことが以下です。
ポイント①:購入前に言葉の説明を子供さんと一緒に確認する
ネット書店や出版社のウェブサイトで内容を確認できるようになっている辞典がほとんどだと思うので、購入前に言葉の説明をお子さんと一緒に確認するのがおすすめです。その辞典の言葉の説明でお子さんはすんなり理解するかどうか、言葉の説明がお子さんにとってわかりやすいものになっているかどうか。
その際、普通名詞の意味はわかりやすいので、抽象的な言葉で試すのがいいと思います。
ポイント②:小6まで使う前提で選ばない
全学年対象になっている国語辞典が多いですが、低学年の子供用に国語辞典を買うのであれば、小6まで使う前提で選ばない方がいいと思います。
小1~小2と、小5~小6では国語力が全然違いますよね。『新レインボー』も全学年対象になっていますが、中学年以上が使う作りになっている印象です。小1~小6の間に辞典を買い替える前提で選ぶのがいいと思います。
おまけ:直感を無視しない
私は『チャレンジ』がすごく使いやすそうだと感じていたのに、収録語数の少なさや出版年が古いことがどうしても気になってしまい、『新レインボー』を選びました。でも、その後も『チャレンジ』がずっと気になっていて、買わなかったことをすごく後悔。そして、最近、結局『チャレンジ』を買いました。
「使いやすそう!」みたいなポジティブな感覚がある場合は、その感覚を無視しない方がいいかもしれません。
最後に
私はしっかり比較検討した上で良い国語辞典を選んだつもりでしたが、息子にとって言葉の説明が難しかったため、言葉の意味を調べても「なるほど!」とはならないことがほとんどで、結局その辞典は使わなくなってしまいました。
いくら収録語彙数が多くて、写真・イラストが豊富で、発売日が新しくても、辞典を使う子にとって言葉の説明が難しくて使わなくなったら意味がありません。
とにかく、言葉の説明がわかりやすい国語辞典を選ぶことをおすすめします。
それでは、また!